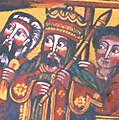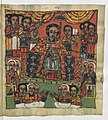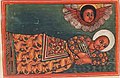ソロモン朝
| ソロモン朝 | |
|---|---|
 | |
| 国 | エチオピア帝国 |
| 当主称号 | ネグサ・ナガスト |
| 創設 | 1270年 |
| 家祖 | イクノ・アムラク[注釈 1] |
| 最後の当主 | ハイレ・セラシエ1世 |
| 滅亡 |
1936年(第二次エチオピア戦争による亡命) 1974年9月12日(エチオピア革命による退位) |
| 民族 | 主にアムハラ族[1] |
| 著名な人物 | メネリク2世 |
ソロモン朝(ソロモンちょう、英語: Solomonic dynasty, House of Solomon)は、エチオピア帝国の王朝である。1270年にイクノ・アムラクによって創始され[1]、1974年のエチオピア革命によるハイレ・セラシエ1世の退位まで存続した。キリスト教を基盤とする王朝である[2]。
概要
[編集]諸王と版図の変遷
[編集]| エチオピアの歴史 |
|---|
 |
| アクスム王国 |
| ヌビア(ヌビア王国) |
| ザグウェ朝 |
| ソロモン朝 |
| ムダイト朝 |
| オーッサ・スルタン国 |
| ヤジュ朝 |
| エチオピア帝国 |
| テオドロス朝 |
| 復古ザグウェ朝 |
| ティグレ朝 |
| 近代エチオピア |
| 復古ソロモン朝 |
| イタリア領(サヴォイア朝) |
| イギリス軍政 |
| 復古ソロモン朝 |
| 臨時軍事行政評議会 |
| エチオピア |
エチオピアの伝説『諸王の栄光』によると、メネリク1世は、エチオピアのシバの女王と、イスラエル王国の王、ソロモンとの間に生まれたとされている[注釈 2][3]。1270年、イクノ・アムラクはその後裔を自称し、ザグウェ朝を打倒して、ソロモン朝を創始した[1][4]。これは血統的に、アクスム王国の復活を意味した[3]。

王朝成立前の10世紀ごろから、アデン湾沿岸とエチオピア高原を結ぶルートを介して、ムスリム商人がソロモン朝の領内に訪れるようになった[5]。14世紀前半、ソロモン朝はアムダ・セヨンの統治下で版図を拡大させていったが[6]、ムスリム勢力の侵攻が始まり、両者の攻防は拮抗するようになった[5]。
15世紀にはソロモン朝は最大版図を達成したが、16世紀から、ジハードを唱えるアフマド・グラニが先導するムスリムの大軍勢に圧倒され滅亡の危機に陥った[5]。ムスリム勢力は、キリスト教の教会や修道院を破壊し、領内の主要な州を占領し、キリスト教信者に改宗を迫った[7]。しかし、大航海時代のさなかエチオピアを訪れていたポルトガル人を通じて、キリスト教軍がソロモン朝に加勢し、アフマド・グラニは戦死した[5]。16世紀後半になると、オロモ人の侵攻を受けて、ソロモン朝含むキリスト勢力とムスリム勢力の双方は弱体化した[5]。結果としてソロモン朝はエチオピア高原南部の領土を多く失い[1]、版図は半分にまで減少した[2]。
その後、ゴンダールへの遷都以前の期間であるプレ・ゴンダール期(1540年 - 1632年[2])より、帝国は再建の道を歩むことになるが、帝国の軍事の中枢である王直属の地方駐屯部隊、チャワは同期ごろには機能しなくなり、ススネヨスの治世までに崩壊した[8]。再建のさなかである1632年、ファシラダスは、侵攻による被害が少なかったゴンダールへ遷都し、ゴンダール期(1632年 - 1769年)と呼称される時期が始まった[注釈 3][1]。同期前半にはイヤス1世が主導して帝国の再建を実施し[1]、オロモ人による侵攻によって失った領土を回復するに足る国力を得た[2]。外部勢力からの侵攻のさなか、特にファシダラスの治世下において、統治に関する政策にも変容がみられ、16世紀以降は、王朝の権力の弱体化とともに州統治者の権力増大が進んだ[7][10]。王権が形骸化し、地方の統治者が台頭したにも関わらず、19世紀に至るまでソロモン朝に代わる新たな王朝が成立しなかった要因については、現在も解明が進んでいない[2]。
1706年、イヤス1世は暗殺され、続く15年間は、皇帝の暗殺や政争が頻繁に発生した[1]。この時期を経て1721年にバカッファは皇帝に即位した[1]。バカッファは、前述のように形骸化しつつあった王権を、反対派の弾圧を通して復活させ、政情の安定化を一時的に達成した[1]。しかし、2代後のイヨアス治世下では州統治者間の争いにより再び政情は不安定となり、彼はティグレ州のミカエル・セフルの助力を得て事態の収束を図るもかなわず、結局1769年に暗殺された[1]。その後、ソロモン朝の権威は再び形骸化、名目化し、各地の有力者が群雄割拠する「士師時代」(1769年 - 1855年)に突入した[1]。
先述の混乱を経て、1855年に即位したテオドロス2世は、帝国を再統一し、イギリスから武器製造の職人を呼び集めるなど、近代化に努めた[11]。しかし、イギリスとの対立から、1868年に彼は処刑された[7]。
テオドロス2世の死から4年経過した1872年1月21日に、ヨハネス4世が後継者争いの後に即位した[7][12]。即位に関しては、ショアの首長、サーレ・マリアム(のちのメネリク2世)と対立したものの、ヨハネス4世の息子とサーレ・マリアムの娘が結婚し、サーレ・マリアムの次期即位が確定したために、対立は沈静化した[12]。また1870年代には、イスマーイール・パシャ率いるエジプト軍に侵攻されたが、これを撃破した[12]。
1883年、アディスアベバ[注釈 4]が建設され[13]、1889年に即位したメネリク2世は、同年よりこの地を新たな首都とした[14]。1889年5月2日、彼はイタリアとウッチャリ条約を締結し、国家の平和的統一を図ったが、1891年3月24日に締結されたローマ議定書で、エチオピアはエリトリアに対する支配権を失った[7]。さらに1896年、これに乗じて植民地拡大を目論んだイタリアはエチオピアを侵略したが、アドワの戦いでメネリク2世はこれを撃退した[7](第一次エチオピア戦争)。同年、アディスアベバ条約でエチオピアの独立性を確保した[15]。また同年、ソマリア領のオガデン地方を併合し、版図を拡大させた[15]。

1930年、女帝ザウディトゥが死去し、これを受け、メネリク2世の従弟、王子ラス・タファリ・マコンネンの息子にあたる[16]ハイレ・セラシエ1世が皇帝に即位した[17][18]。1935年、ベニート・ムッソリーニ政権下のイタリアが再びエチオピアに侵略し、全土を支配した(第二次エチオピア戦争)。このため、ハイレ・セラシエ1世はイギリスに亡命した。亡命の間、エチオピアはイタリア領東アフリカとして統治された。1941年、彼はイギリスとともに祖国解放の進軍を行い、同年5月に独立を回復した[19]。
1955年11月5日、ハイレ・セラシエ1世は、彼が以前制定した1931年エチオピア帝国憲法をさらに明確化して、皇帝への権力の集権化を盛り込み、1955年エチオピア帝国憲法を公布した[7]。そして1960年12月14日、彼がブラジルを訪問している最中に、1960年エチオピアクーデターが発生し、ソロモン朝は窮地に立たされたが、国王の緊急的な帰国により、まもなく鎮圧された[7]。
1974年1月12日に急進的な近代化政策の末、エチオピア革命が勃発。最終的に1974年エチオピアクーデターによりハイレ・セラシエ1世は同年9月、退位に追い込まれた[19]。同年、エチオピア当局に逮捕され、翌年に死去した。また、皇帝の身柄拘束と同時に、1955年エチオピア帝国憲法は停止され、ついに3000年の歴史を持つエチオピア帝国は終焉を迎えた[7]。
宗教史
[編集]単性論派の一派であるエチオピア正教会が4世紀以降、エチオピアに拡大した[20]。その後ムスリム勢力で圧迫されたが、1270年ごろ、タクラ・ハイマーノトの努力により、ソロモン朝の創始とともにエチオピア正教会は活力を取り戻した[20]。最大版図を擁していた15世紀ごろは、教会は大土地所有者として国政への影響を強めた[20]。続く16世紀、領内に侵攻したムスリム勢力に対抗するための、ポルトガルからの援助と引き換えに、エチオピア正教会とカトリックとの教会合同が強く働きかけられた。そしてプレ・ゴンダール期の1626年、皇帝スセンヨス[7]がカトリックへと改宗し、布教にはイエズス会が関係した[20]。しかし、武力を背景にした布教であったために、1632年[7]に追放され、エチオピア正教会が復活した[20]。
文書にみる王朝
[編集]ソロモン朝の年代記においては、紀元前5508年を天地創造の年として、これを紀元とする、独自の暦がしばしば用いられていた[21]。また、ソロモン朝が終焉を迎える1974年まで、エチオピア帝国憲法には、メネリク1世からハイレ・セラシエ1世に至るまで血続きである旨が記されており、伝説とされる部分も史実として重要視されていたことを意味する[7][22]。
歴代皇帝
[編集]脚注
[編集]注釈
[編集]出典
[編集]- ^ a b c d e f g h i j k 石川博樹 (1998年4月20日). “エチオピア王国ソロモン朝の衰退と州統治者 : ゴンダール期(一六三二〜一七六九)における統治者称号の分析を通して”. J-STAGE. pp. 1-2. 2025年2月8日閲覧。
- ^ a b c d e 石川博樹. “ソロモン朝後期に於ける北部エチオピアのキリスト教王国—オロモ進出後の王国史の再検討—(石川 博樹)”. 東京大学大学院人文社会系研究科・文学部. 2025年2月9日閲覧。
- ^ a b “ViewPoint15 世界で最も歴史深い国、エチオピア”. 駐日エチオピア大使館. 2025年2月9日閲覧。
- ^ 石川博樹 (1998年4月20日). “エチオピア王国ソロモン朝の衰退と州統治者 : ゴンダール期(一六三二〜一七六九)における統治者称号の分析を通して”. J-STAGE. p. 33. 2025年2月8日閲覧。
- ^ a b c d e “16世紀までのエチオピアのイスラーム”. 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所. 2025年2月9日閲覧。
- ^ 「エチオピア」『世界大百科事典(旧版)』平凡社。コトバンクより2025年2月10日閲覧。
- ^ a b c d e f g h i j k l 吉川智. “エチオピアの君主制度について ―皇帝の地位と権能及びその君主制崩壊の原因をめぐって―”. 国士舘大学 学術情報リポジトリ. pp. 90-97. 2025年2月10日閲覧。
- ^ 石川博樹 (1998年4月20日). “エチオピア王国ソロモン朝の衰退と州統治者 : ゴンダール期(一六三二〜一七六九)における統治者称号の分析を通して”. J-STAGE. p. 13. 2025年2月9日閲覧。
- ^ 「ゴンダル」『百科事典マイペディア』平凡社。コトバンクより2025年2月9日閲覧。
- ^ 石川博樹 (1998年4月20日). “エチオピア王国ソロモン朝の衰退と州統治者 : ゴンダール期(一六三二〜一七六九)における統治者称号の分析を通して”. J-STAGE. p. 2. 2025年2月9日閲覧。
- ^ 「テオドロス2世」『ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典』ブリタニカ・ジャパン。コトバンクより2025年2月9日閲覧。
- ^ a b c 「ヨハネス4世」『ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典』ブリタニカ・ジャパン。コトバンクより2025年2月9日閲覧。
- ^ a b 「アディスアベバ」『百科事典マイペディア』平凡社。コトバンクより2025年2月9日閲覧。
- ^ 「アジス・アベバ」『山川 世界史小辞典 改訂新版』山川出版社。コトバンクより2025年2月9日閲覧。
- ^ a b 「メネリク2世」『改訂新版 世界大百科事典』平凡社。コトバンクより2025年2月9日閲覧。
- ^ 「ハイレ・セラシエ」『日本大百科全書(ニッポニカ)』小学館。コトバンクより2025年2月9日閲覧。
- ^ 「ハイレ・セラシエ」『ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典』ブリタニカ・ジャパン。コトバンクより2025年2月9日閲覧。
- ^ 「ハイレ・セラシエ1世」『20世紀西洋人名事典』日外アソシエーツ。コトバンクより2025年2月9日閲覧。
- ^ a b 「エチオピア史」『ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典』ブリタニカ・ジャパン。コトバンクより2025年2月8日閲覧。
- ^ a b c d e 「エチオピア教会」『改訂新版 世界大百科事典』平凡社。コトバンクより2025年2月9日閲覧。
- ^ 石川博樹 (1998年4月20日). “エチオピア王国ソロモン朝の衰退と州統治者 : ゴンダール期(一六三二〜一七六九)における統治者称号の分析を通して”. J-STAGE. p. 32. 2025年2月10日閲覧。
- ^ 諏訪兼位「エチオピア」『日本大百科全書(ニッポニカ)』小学館。コトバンクより2025年2月8日閲覧。